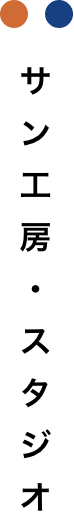豊田市、岡崎市で和モダンの木の家をお考えの方へ【格子を通して見えるもの。】~木の家設計作法-其の513~
格子の表構えの家々が軒を連ねる風景には、日本人なら誰しもが、どこか懐かしさを覚えます。
格子は日本建築や住宅において様々な役割を果たしてきました。
私たちもこれまでたくさんの格子を設計してきましたが、ここで格子の役割についてしっかりおさらいをしてみたいと思います。
日本建築における格子の役割
① 通風・採光
-
格子は隙間があるため、風通しが良く、光を柔らかく取り込むことができます。
-
特に夏の蒸し暑い気候に対応した、自然の風を活かした涼の工夫の一つです。
-
格子越しに差し込む光はやわらかく、室内の明暗のコントラストが美しくなります。
② 視線の調整(プライバシー)
-
外からは中が見えにくいけれど、中からは外の様子がうっすら見える、という視線の調節機能。
-
プライバシーを保ちながらも閉塞感を与えないのが特徴です。
③ 防犯
-
窓や戸の外側に格子をつけることで、不審者の侵入を防ぐ効果があります。
-
特に町家(まちや)などの市街地の家屋では、防犯と通風を両立する工夫として重要です。
④ 美的要素・デザイン
-
格子のパターンには地域ごとの特徴や、家の格(地位)を示す意味がある場合もあります。
-
京町家の「出格子」や「虫籠窓(むしこまど)」など、伝統的な意匠が豊かです。
-
シンプルながらも繊細な美しさが、日本建築の美意識を体現しています。
⑤ 軽量で可変性がある
-
木材で作られるため軽く、建具として可動性が高いのも特徴です。
-
必要に応じて開け閉めしたり、取り外したりすることで、空間の使い方を柔軟にできます。

「あかりをつつむ平屋」 (ガレージと中庭のある平屋) 詳しくはこちら
上記のように格子は和の趣を感じさせる意匠の役割と同時に、空間を仕切るという役割が大きいと思います。
家の内部と外部の間に設置された格子は、仕切って隠すと同時に光や風を通すことで、内部からは外の様子をうかがい知ることができます。
また逆に外部からの視線に対しては、完全に遮断するのではなく、そこはかとなく気配を感じさせることで、やんわりと内と外をつないでくれます。
このようにふたつの境界を“あいまい”に分ける格子は日本文化特有の手法でもあり、
日本人独特の美意識とともに、今後も日本の街並みや家並みを形成する要素になり得ると考えます。
サン工房・スタジオ代表:袴田英保

「うたう坂の家」 (大きな格子戸のある家) 詳しくはこちら