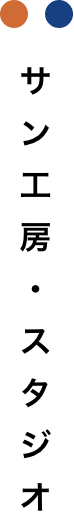名古屋市で注文住宅をお考えの方へ/サン工房・スタジオ/【光と風と語り合うくらし】~木の家設計作法-其の533
住まいの快適性はどこからもたらされるのでしょうか。
美しい外観。広々とした空間。お気に入りのインテリア。便利な住設機器。
もちろんそうした物としての要素も重要です。
しかし、それらだけでは住まい手の情感や心持ちまでも十分に満足させることはできません。
人間としての遠い記憶を内に秘めた住まい手は、外から入る光や風といった自然を肌で感じてこそ、心身ともに心地よさを感じるからです。
窓から差し込む太陽の光は、単に明るさやあたたかさをもたらすだけでなく、空間に多彩な表情を与えてくれます。
そして風は高温多湿の日本の夏に涼しさを運び入れてくれるとともに、一年を通じて自然の息づかいを感じさせてくれます。
「光と風と語り合う暮らし」は、私たちが家づくりにおいて特に大切にしているコンセプトであり、自然の光と風を最大限に活用し、住まいの快適性と心地よさを追求する設計思想を表しています。
このコンセプトは、日本の伝統的な住まいの知恵と深く結びついています。
古くから日本の家は、高温多湿な夏と寒い冬という厳しい気候環境に対応するため、様々な工夫を凝らしてきました。
例えば、大きな軒の出で日差しや雨を防いだり、建具の開閉によって風を取り入れて涼んだり、逆に閉め切って暖かさを保ったりするなどのしつらえが多々ありました。
私たちは、こうした日本の家の優れた点を現代の建築技術や高い性能と融合させ、「安心で快適な現代の日本の家」を提案しています。
具体的な「光と風と語り合う暮らし」を実現するための工夫は以下の通りです。
1. 光の取り入れ方と調整
■大開口の窓と軒の出:
リビングやダイニングには、庭や周囲の景色とつながる大きな木製サッシの窓を設けることで、開放感のある空間を創出します。
また、深くせり出した軒は、夏の強い日差しを遮りつつ、冬の低い日差しは室内の奥まで取り入れ、床を温める「ダイレクトゲイン」効果で快適性を高めます。
■間接的な光の活用:
直射日光だけでなく、芝生などからの反射光を室内に取り入れることで、柔らかく落ち着いた明るさの空間を作り出します。
障子や透りガラス、格子戸といった建具は、光を和らげたり、室内の印象を優しく変化させたりする役割を果たします。
照明計画においても、目線の高さを考慮した配置や、トップライトにルーバーを設けることで、光の質にも配慮しています。
■プライバシーの確保:
格子スクリーンや建具の配置を工夫することで、外部からの視線を遮りながらも、光を取り込み、開放感を損なわないデザインを実現しています。
2. 風の通り道と換気
■回遊動線と窓の配置:
間取りに回遊性のある動線(回れる動線)を取り入れることで、家の中に複数の風の通り道を作り、自然でスムーズな空気の流れを促進します。
これにより、特に季節の良い時期には、窓を開けるだけで家全体が快適な空間となります。
■ 自然素材の調湿性:
無垢の木材や漆喰などの自然素材は、湿度を吸放湿する優れた特性を持っています。
これにより、梅雨の時期でもジメジメすることなく心地よく過ごせ、エアコンに頼りすぎない快適な室内環境を保ちます。
私たちサン工房・スタジオは、これらの工夫を通じて、単なる物理的な快適さにとどまらず、自然を身近に感じ、心が癒されるような豊かな暮らしを「光と風と語り合う暮らし」として提供しています。
サン工房・スタジオ代表:袴田英保
 「光を温く家」(増築二世帯住宅の家・窓を工夫した家) 詳しくはこちら
「光を温く家」(増築二世帯住宅の家・窓を工夫した家) 詳しくはこちら
 「光を温く家」(増築二世帯住宅の家・窓を工夫した家) 詳しくはこちら
「光を温く家」(増築二世帯住宅の家・窓を工夫した家) 詳しくはこちら