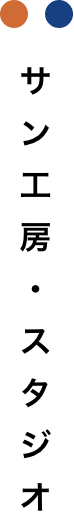豊田市で和モダン注文住宅を建てるなら【風合いを生かす】~木の家設計作法-其の540~
私たちがつくる木の家においては様々な無垢の自然素材の風合いを楽しめます。
「無垢の木」「左官」「石」「和紙」といった自然素材の風合いを生かした設計は、素材そのものの持つ質感・経年変化・光との関係性を設計の中心に据えることで、空間に深みと静けさを生み出します。以下に、そのような設計を考える上でのポイントを整理したいと思います。
1.素材の個性を理解する
-
無垢の木:木目や節、色味の違いなど、一つひとつの表情が異なります。経年変化で飴色に変わる様子も美しいものがあります。私たちは無垢の木を構造材・仕上げ材・家具など多用途に使います。
→ 例:床はオークやナラの素材で力強く、天井は杉で優しく柔らかい素材を使用など。 -
左官(塗り壁):湿気を吸ったり吐いたり、匂いを吸収したりと呼吸する素材です。光の当たり方で陰影が生まれ、土や珪藻土、漆喰などで風合いが変わります。
→ 例:外壁は荒い仕上げで力強く、内壁は細やかでやわらかな表情に仕上げるなど。 -
石:重厚感と安定感を与える素材です。磨き・割肌・錆などの仕上げで印象が大きく変わります。
→ 例:玄関の床や庭の縁石などに用いて、空間の基礎的な“重さ”を演出します。 -
和紙:柔らかく光を透かす性質があり、空間に温もりをもたらしてくれます。
→ 例:障子や照明、壁の一部に用いて、光をやわらかく拡散させます。
2.素材を引き立てる設計の工夫
-
素材を混ぜすぎない
多種類を使うときは、主素材と補素材を明確にし、全体の統一感を保ちます。
例:床=木、壁=左官、天井=木 or 和紙調など。 -
自然光との関係を意識する
木や左官、和紙は光によって風合いが生きます。
→ 朝・昼・夕の明るさの変化や光の入り方が素材の表情を豊かにする設計を意識します。 -
経年変化をデザインに組み込む
新築時の美しさよりも、10年後・20年後の味わいを見越して設計します。
→ メンテナンスしながら長く使えるような素材構成を検討します。 -
触感と温度感
手触り・足触りの良さを重視する。素材の「温もり」「ひんやり感」を意識して配置します。
→ 木=リビング床、石=玄関や水まわり、和紙=寝室や書斎の壁など。
3.和の設えとの調和
-
間(ま)と余白を活かす
素材が主張しすぎないよう、空間に「静けさ」と「余白」を設けます。 -
陰影礼賛的な光の扱い
直射よりも反射光や漏れ光で素材の質感を表現します。 -
自然とのつながり
素材が自然から生まれたものであることを意識し、庭や外部との連続性を大切にします。
4.まとめ
無垢の木が「温かさ」を、
左官が「静けさ」を、
石が「安定感」を、
和紙が「やわらかさ」を空間にもたらす。
それぞれが互いを引き立て合うように設計することで、素材の「風合い」が生きる家になると思います。
そして素材の風合いと個性を生かすのは、職人の目であり、技だと思います。
私たちの家づくりは、そのような素材の風合いとそれを生かす技術により支えられています。
代表:袴田英保

「風光る平家」(中庭のある平家・ガレージがある平家) 詳しくはこちら