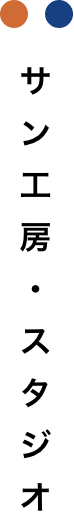豊田市で和モダンな木の家をお考えの方へ/サン工房・スタジオ【街並みをつくる】~木の家設計作法-其の509~
かつての日本の街並みは、屋根の素材や形などが統一され、それは美しいものがありました。
しかしながら、昭和になって、様々な建築素材が開発され、高度経済成長とともに、
爆発的に住宅の数も増えると同時に多様化して行く中で、街並みは本当に崩れてしまいました。

ではかつての日本の街並みが美しかったのはなぜでしょうか?
それは以下のような点から考えられます。
1. 自然と調和した景観
昔の日本の街並みは、周囲の自然と調和するように作られていました。
・木造建築そのものが周囲の山々や森林と一体感があり、季節の移ろいとともに色合いや風合いが変わる。
・庭や植栽には四季折々の植物が取り入れられ、街並みに自然の彩りが加わる。
・石畳や川が配置されることで、水や風などの自然要素が身近に感じられました。
2.素朴で温かみのある建築様式
伝統的な街並みには、木や土壁、和紙などの自然素材が多く使われており、
これが柔らかで温もりのある景観を作り出していました。
・町屋や長屋は庶民の生活感が漂い、親しみやすさを感じさせてくれる。
・寺社仏閣や城下町では、荘厳さと繊細な美しさが共存している。
3.コンパクトで人に優しい街づくり
昔の日本の街は徒歩や自転車で移動できるサイズ感で設計されていました。
・細い路地や曲がりくねった道は、偶然の出会いや景色の変化を楽しむ要素になっている。
・小さな橋や石灯など、さりげない装飾が街の風情を引き立てている。
4.歴史と文化が息づく風景
古い街並みにはその土地の歴史や文化が染み込んでいます。
・古民家や武家屋敷は昔の暮らしの面影を残し、懐かしさや郷愁を感じさせてくれる。
・宿場町や城下町には旅人を迎える情緒があり、歴史を感じることができる。
5. 照明や装飾の控えめな美しさ
昔は電灯が少なく、夜は月明かりや行灯(あんどん)、提灯が街を照らしました。
・優しい光が街並みに影を落とし、幻想的で風情ある夜景を作り出しました。
・看板や広告が少なく、シンプルで落ち着いた景観が保たれている。
これからの日本の街並みについて考えると、よほど国が規制を敷かない限り、残念ながら上記のような美しさを取り戻すことはないと思われます。
そのような状況の中でも、住宅に携わる私たちは、街並み全体をつくるところまではできないまでも、
その一軒が街並みを作って行くという気概を持って、丁寧に設計していく姿勢を持たなければならないと思います。
サン工房・スタジオ 代表取締役:袴田英保

「勇慕連の家」(街中の家・地域と生きる家)詳しくはこちら